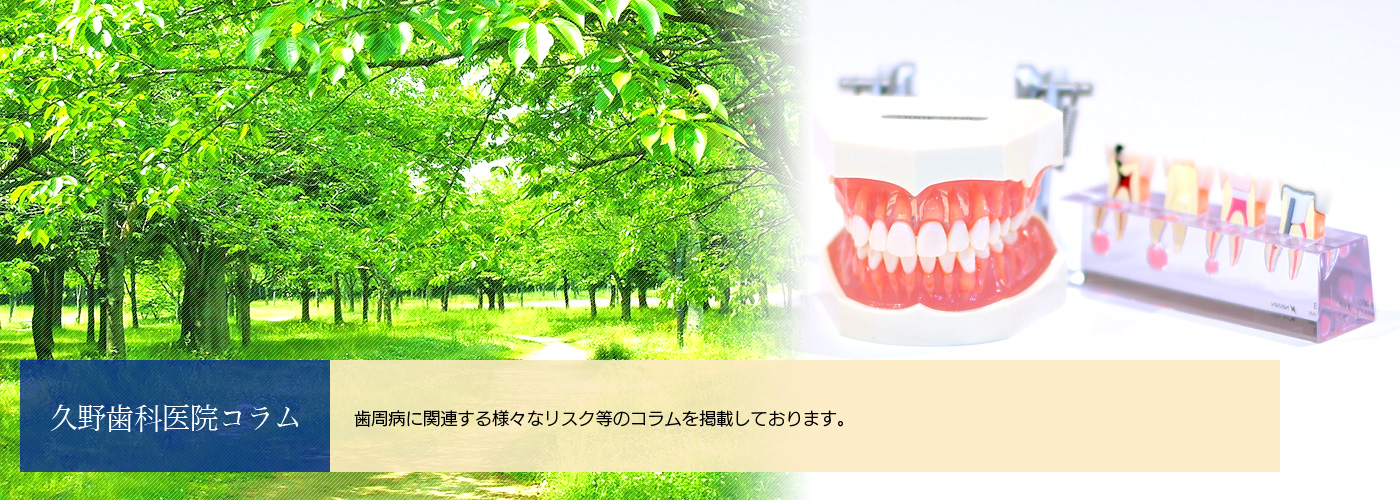

 |
 |
 |
当院おすすめ記事はこちら▼
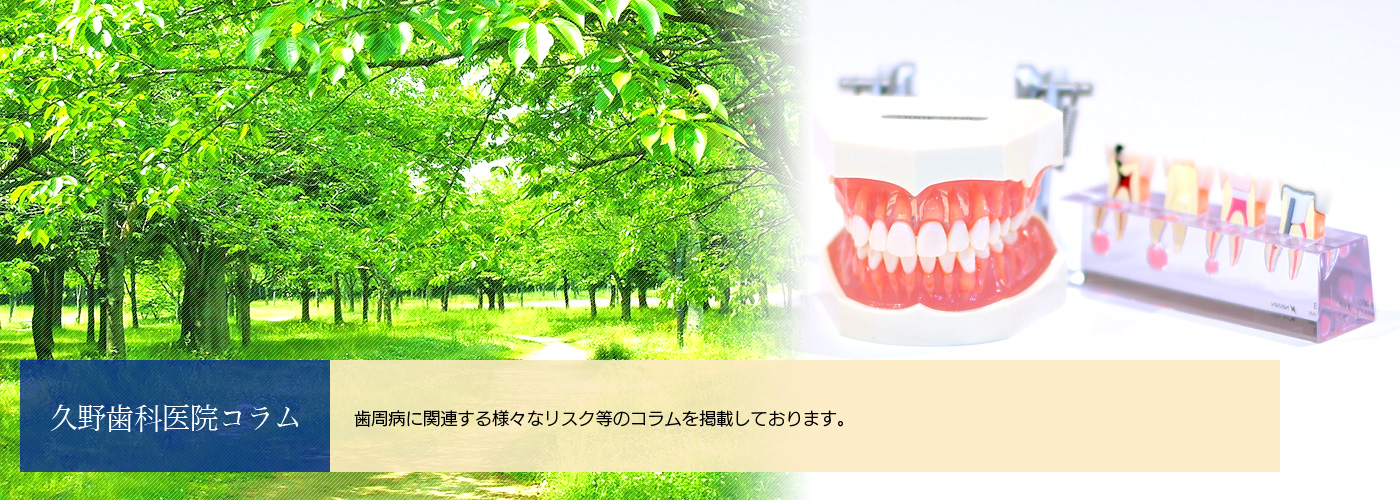

常滑の矯正歯科 久野歯科医院 ≫ 久野歯科医院コラム
常滑市の歯医者、久野歯科医院です。
皆様の役に立つ情報をお届けいたします。
 摂食嚥下障害とは食物を認識し、口に食物を運び入れて飲み込む
摂食嚥下障害とは食物を認識し、口に食物を運び入れて飲み込む
までの一連の、ものを食べる機能の障害のことです。
以下のような症状がみられたら、摂食嚥下障害が疑われます。
■ 摂食嚥下障害の症状
1.食事中にむせることがある。
「むせ」は嚥下障害を疑う重要な兆候です。
「さらさらの液体」や「ぱさぱさの食物」など食品の性状について注意が必要です。
2.食後によく咳き込む。
食後に気管に食物の残りが流れ込むと咳き込みます。
3.痰がよく絡む。
食物が気管に流れ込むと痰が多く排出されます。
痰の中に食物が混じっていると注意が必要となります。
4.よだれが多くなる。
1日の唾液の分泌量は平均で1リットル〜1.5リットルです。
飲み込み(嚥下)が難しくなるとお口の中の唾液が飲み込めず、よだれが多くなります。
5.飲み込みにくい食べ物がある。
唾液によって作られる食べ物の塊(食塊)がうまくできません。
性状がぱさぱさの食べ物や繊維質の食べ物は食べ物の塊が形成しにくいのです。
6.食後にかすれたような声、ガラガラした声のように声に変化が起こる。
声は声帯から発せられ口の中や鼻に抜けて音になります。
食後に声帯の近くに食べ物が残ってしまうと声に変化が起こります。
7.食べ物をよくこぼすようになる。
麻痺がありますと唇をうまく閉じることができず食べ物をよくこぼすことがあります。
8.食事の時間がのびた。
摂食嚥下の工程に問題があることが推測されます。
食事時間の延長はかえって疲労を招き、誤嚥の可能性を高めてしまいます。
食事は1時間以内とします。
9.飲み込んだ後に食べ物がお口のなかに残る。
1回の嚥下で20ml〜30mlが食堂に移行します。
麻痺などがあり、摂食嚥下機能が低下してくると食べ物がお口の中に残ります。
10.舌の上(舌背)が白くなっている。
舌の運動や唾液の分泌の低下などに問題が生じると「舌苔」が現れてきます。
舌ブラシなどを利用してやさしく舌苔を取り除きます。
激しく除去すると味蕾を損傷し味覚障害がでる可能性があります。
舌苔は口臭の原因となります。
摂食嚥下機能訓練とは食べ物や飲み物をうまく飲み込めるように開発された訓練です。
お口の周りの筋肉を鍛えるように訓練をします。
食べ物を使用しないので間接訓練といいます。
食事の姿勢や食事に費やす時間、飲み込みやすい食べ物についての指導を受けることも大切です。
1.深呼吸(腹式呼吸)
口から息を吐きます。できるだけ全部吐くような感覚で息を吐いていきます。
次に口を閉じて鼻から大きくゆっくり息を吸い込みます。
おなかに手を当てて行うと実感できます。
2.首の運動
左右に首を回して後ろを見るようにします。
次にまっすぐ前を向き、首を肩につけるように傾けます。左右行ないます。
3.肩の運動
両肩をすぼめるように上げて、すっと力を抜きます。
次に両肩をまわします。
4.口の運動
唇を突き出したり(ウの発音)唇を横に引いたりします(イの発音)
5.舌の運動
舌を出したり引っ込めたりをくりかえします。
舌を左右に動かして唇の横(口角)をなめます。舌打ち、舌鼓をします。
6.発音の練習
「パ・パ・パ」「タ・タ・タ」「カ・カ・カ」と繰り返し発音します。
早口言葉や替え歌なども練習材料として適当です。
7.唾液腺のマッサージ
加齢が原因で唾液の分泌能力が低下したり基礎疾患があり、
いつも飲んでいるお薬の副作用の影響などでお口が渇きやすくなります。
3大唾液腺のマッサージを行い唾液の分泌をうながします。
唾液腺のマッサージにつきましてはドライマウスについて(1)を参考にして下さい。
他にもお口のエクササイズにはみらいクリニックの今井一彰先生(内科のお医者様)が
考案されたあいうべ体操も非常に有効です。
唾液の分泌では早いひとで1週間で効果があらわれます。
当院ではドライマウスの患者様や入れ歯の不具合の方にもお話して実行を促しています。
お口の周りの筋肉を鍛えて呼吸を整えます。
コップに水を入れて、ストローで息を吐きぶくぶくと吹きます。
5回行ないます。
お口に空気を入れ頬を膨らませたり、へこませたりします。
10回行ない、それを1セットとして2〜3セット行ないます。
咳をすることはのどの奥に入ったものを吐き出し誤嚥を防ぎます。
お腹に手を置き腹筋を使って、勢いよく咳をします。
飲み込んだ後咳をします。
声帯の動きをよくして気道への入り口を閉じる働きをよくします。
誤嚥を予防する訓練です。
壁を押しながら力を込めて「エイ!」「ヤ!」などの声を出します。
力強い声を出すことが大切です。
5〜10回行ないます。
それを1セットとして1日2〜3セット行ないます。
嚥下と呼吸の協調・タイミングを整え,誤嚥を起こしにくい飲み込み方を習得する訓練です。
深呼吸を顎を上げないようにします。鼻から大きく吸ってしっかり息を止めます。
唾液や空気を飲み込みます。息を吸わずに勢いよく息を吐きます。
食道の周りの筋肉を強化して食べ物が食道に入りやすくします。
固いマットに仰向けに寝て、下顎の先を胸に近づけるように頭を持ち上げます。
その状態を5秒ぐらい保ちます。肩がマットから離れないように注意して
腹筋を使わないようにして口はしっかりと閉じます。
10回行ないます。これを1セットとして3セットを1日3回行ないます。
口腔機能の向上とは
お口の中の清掃やお口の中をきれいに保つこと(口腔ケア)と
摂食嚥下機能訓練のことをいいます。
口腔ケアは
セルフケア(自分で行う口腔ケア)と
プロフェショナルケア(歯科医師、歯科衛生士が行う専門的な口腔ケア)の
2本立てで行なわれます。
セルフケアは
歯ブラシや補助用具を選んでお口の中をきれいにする。
むし歯の予防、歯周病の予防にくわえ、頬や上顎、舌の汚れを取りきれいにする。
入れ歯を原則として寝る前にははずし、丁寧に扱い清潔に保ちます。
プロフェショナルケアでは
歯の汚れを徐去したりセルフケアでは除去しにくい難しい場所のお口の清掃をします。
お口の状況にあわせた口腔ケアのアドバイスをします。
個人の状況を考えた入れ歯の手入れや使用方法についても指導いたします。
歯周病やむし歯があったり入れ歯の具合が悪く、ものが食べにくいと毎日の食生活に
影響がでてきます。お口の中に痛みがあったり、入れ歯に痛みがあると誰でも不愉快で
憂鬱な気分になってしまいます。
お口をきれいにすると味がよくわかるようになり食欲が出てきます。
唾液の分泌が促され口臭の発生も低下してきます。
高齢者のQOLに食べる楽しみはおおきく相関しており、
良質な入れ歯を装着している高齢者はQOLが高く、また元気で外出し活動的です。
お口のなかの歯の本数によってかめる食品もかわります。
当然の事ながら歯の多い方が食品の種類も多くなります。
0〜5歯であれば、
うどん、バナナ、ナスの煮付けぐらいしか咬めません。
6〜17歯になりますとそれに加え、
おこわ、せんべい、レンコン、豚肉の厚切り、かまぼこ、キンピラゴボウと増えていき、
18〜28歯になりますと
フランスパン,イカの刺身、酢だこ、たくあん、するめイカと増加し
いわゆる「なんでも食べられる」状態になります。
入れ歯の具合が悪いと調理にも時間がかかり、食事の介助の時間も長時間になります。
一般的な歯科治療とともに口腔機能の向上に努めれば全身の健康の維持につながります。
| 関連記事: | 超高齢者、高齢者、要介護者に歯科のできること |
| 愛知県保険医協会の歯科地域医療研究会への参加の報告 摂食機能の基礎知識と効果的な口腔ケアの実際 |
|
常滑市の歯科、矯正歯科
久野歯科医院 院長