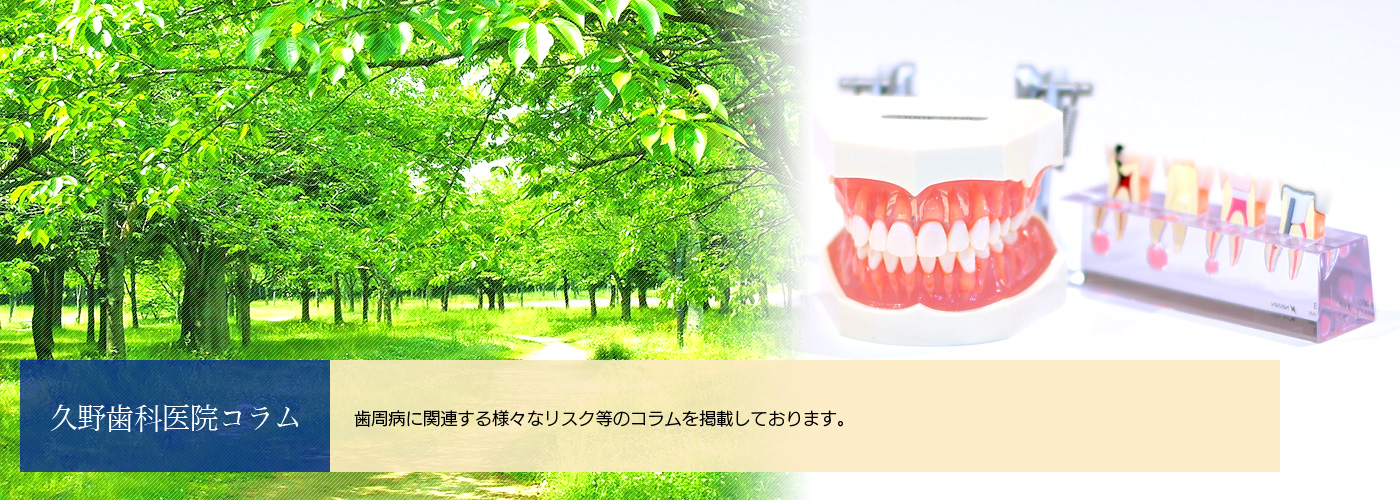

 |
 |
 |
当院おすすめ記事はこちら▼
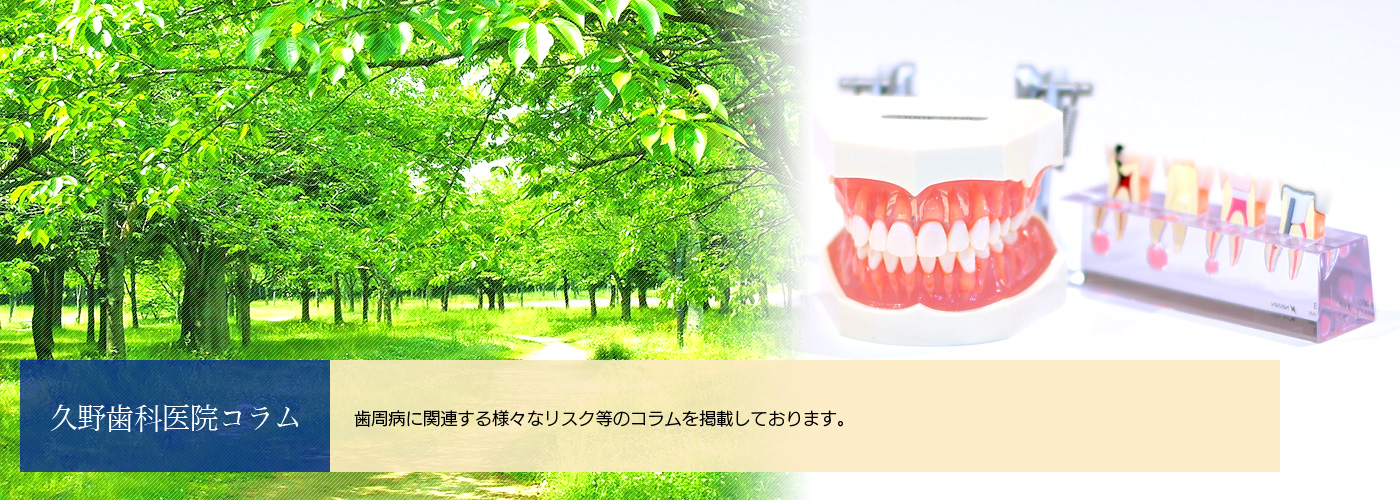

常滑の矯正歯科 久野歯科医院 ≫ 久野歯科医院コラム
 常滑市の歯医者、久野歯科医院です。
常滑市の歯医者、久野歯科医院です。
皆様の役に立つ情報をお届けいたします。
「何か、お薬を飲んでいませんか?」
現在は高齢化社会といわれて久しく、
今後は超高齢化社会になっていきます。
子供のむし歯が減少し、歯科医院に来院される患者様は
中高年の方が多くなってきています。
これからも高齢者の患者様は増加していきます。
多くの高齢者の方は持病を持っていてお医者様から処方されたお薬を常用されています。
歯科で特に注意を要するお薬の代表的なものに
「血液がさらさらになるお薬」「骨粗そう症のお薬」「ステロイド薬」がございます。
 脳梗塞や心筋梗塞などの既往があり、
脳梗塞や心筋梗塞などの既往があり、
基礎疾患をお持ちの患者様は
「血液がさらさらになるお薬」を飲んでいらっしゃいます。
「血液がさらさらになるお薬」は抗血栓薬というお薬で、
大きく分けて抗凝固薬と抗血小板薬があるのですが、
日本国内で現在、抗凝固薬をお使いの方は100万人、
抗血小板薬をお使いの方は600万人いるといわれています。
■ 抗凝固薬について
血栓の形成にフィブリンや赤血球の関与が深い静脈内血栓による血栓症や
不整脈(心房細動)による心原性脳塞栓症予防に使用され、
代表的なものではワルファリンカリウム(ワーファリン)がございます。
2011年より新しい経口の抗凝固薬として
・ダビガトラン(プラザキサ)
・リバーロキサバン(イグザレルト)
・アピキサバン(エリキュース)
・エドキサバン(リクシアナ)
が相次いで使用が承認されました。
新しい経口の抗凝固薬はワーファリンに比べて、血中濃度が安定しているという特徴がございます。
そのためにワーファリンに必要なモニタリング・監視の必要がないといわれています。
新しい経口の抗凝固薬は消炎や抜歯後の感染予防に使用する
抗菌薬(ジスロマック、クラリス、クラリシッド)に
薬の効果に作用するものがあり、注意を要します。
■ 抗血小板薬について
血栓の形成に血小板の関与が深い脳梗塞、心筋梗塞を再発を予防するために使用されます。
代表的な抗血小板薬は
・アスピリン(バイアスピリン)
・ 塩酸チクロピジン(パナルジン)
・硫酸クロピドグレル(ブラピックス)
・シロスタゾール(プレタール)
・ べラプロストナトリウム(プロサイリン)
・ イコサペント酸エチル(エパデール)
などが使用されています。
アスピリンはアメリカでは心筋梗塞などの心臓病の予防に使用され、
パナルジンは白血球などの血液細胞を減少させる副作用のため最近は使用が減っています。
プレタールは認知症の治療薬としても使用されています。
血液がさらさらになるお薬は血栓(血の塊)ができて、血管に詰まることによって起こる
脳梗塞や心筋梗塞などを防ぎ、とても優れた効果がありますが
歯科治療で歯を抜くなどの外科処置を行う時には血が止まりにくく、
処置に予想外に非常に時間がかかる場合も多くあり、歯科治療の障害になってしまいます。
しかし「歯を抜く時に血が止まらないと困る」と
抗血栓薬のお薬を休薬(一時薬をやめる)することをしてはいけません。
抗血栓薬を休薬した方の100人に1人に血栓が原因の発作が起きて
そのうちの80%がなくなっているという報告があり、
抗血小板薬の中断による脳梗塞の発症リスクは3.4倍に上昇するという記載があります。
抗血栓薬を休薬することなく安全に歯を抜くために、
歯科医と持病の主治医が連携をとって
歯科治療をすすめていきます。
特にワーファリンを服用されている方は
INR値という血液の凝固指数の検査をお願いいたします。
INR値はワーファリンの投薬のさじ加減を決める重要な数値です。
血液検査でINR値が3.0以下であれば止血処置をしっかりして、
お薬をつづけながら歯を抜くことができます。
抗血小板薬を飲んでいる方も止血処置をしっかり行うことで歯を抜くことができます。
最近ではお薬手帳を提示していただける機会もおおく、
初診時の問診時に「血液がさらさらになる薬を飲んでいます」と
お知らせいただきますと止血の準備を整えて
治療時間を十分確保して来院をお待ちすることができます。
止血処置の方法は歯を抜いた跡に止血剤を入れ、
傷口を縫合しその上から硬く重ねた小折ガーゼをしっかりとしばらく咬んでいただいて止血します。
喘息やリウマチ、全身性エリテマトーデス(SLE)に代表される
膠原病、アレルギー疾患などの治療に使用されるステロイド薬は、
体のなかの副腎という臓器から出る副腎皮質ホルモンと同じ働きをするお薬です。
免疫反応を抑え炎症やアレルギーの痛みやかゆみを穏やかにします。
喘息やリウマチ・膠原病などのつらい症状を楽にする効果を持っています。
■ 代表的なステロイドの飲み薬
・プレドニン
・プレドニゾロン
ステロイド薬は長期の使用されている方が多く、免疫反応を抑えるので
免疫機能が低下する副作用でむし歯や歯周病が悪化しやすく
歯を抜くなどの外科処置を受けると細菌感染を起こしやすくなります。
ステロイド薬の長期の使用でストレスを和らげる働きのある
副腎皮質ホルモンが副腎から出にくくなり、
歯科治療のような緊張してストレスの多く加わったときに
副腎皮質ホルモンが不足してショック症状(副腎クリーゼ)を起こすことがあります。
ステロイド薬を処方している主治医の先生と連携をとりながら、
歯科治療で加わるストレスの大きさを考えて事前に抗菌薬を処方して、
必要があればステロイドの補充療法などの配慮をして歯科治療を行ないます。
また歯科治療を受けるからと自分の判断で中断しないようにしましょう。
体内のステロイドが急に減少すると危険なうえに症状の悪化を招く恐れがあります。
ステロイド薬の副作用で糖尿病の合併症のある場合や
ステロイド薬は骨をもろくする副作用(ステロイド性骨粗そう症)があり、
そのためにBP(ビスフォスフォネート)剤を飲んでいる方は歯科医にお知らせください。
口内炎の治療などで短期に使用するステロイド軟膏などは問題ありませんが
ステロイド薬を継続的に使用している場合は
歯科医にお知らせください。
また高齢者、超高齢者、被介護者の方は免疫機能が低下し
出血を伴う歯科治療・処置で感染の恐れのある菌血症や心内膜炎などにも注意を要します。
出血を伴う歯科治療・処置を行う場合には事前の抗菌薬(抗生剤)を投与し、
処置後にも必ず抗菌薬を使用して歯科治療を行ないます。
関連記事:骨粗そう症のお薬BP(ビスフォスフォネート)剤・分子標的薬についてはこちら
常滑市の歯科、矯正歯科
久野歯科医院 院長