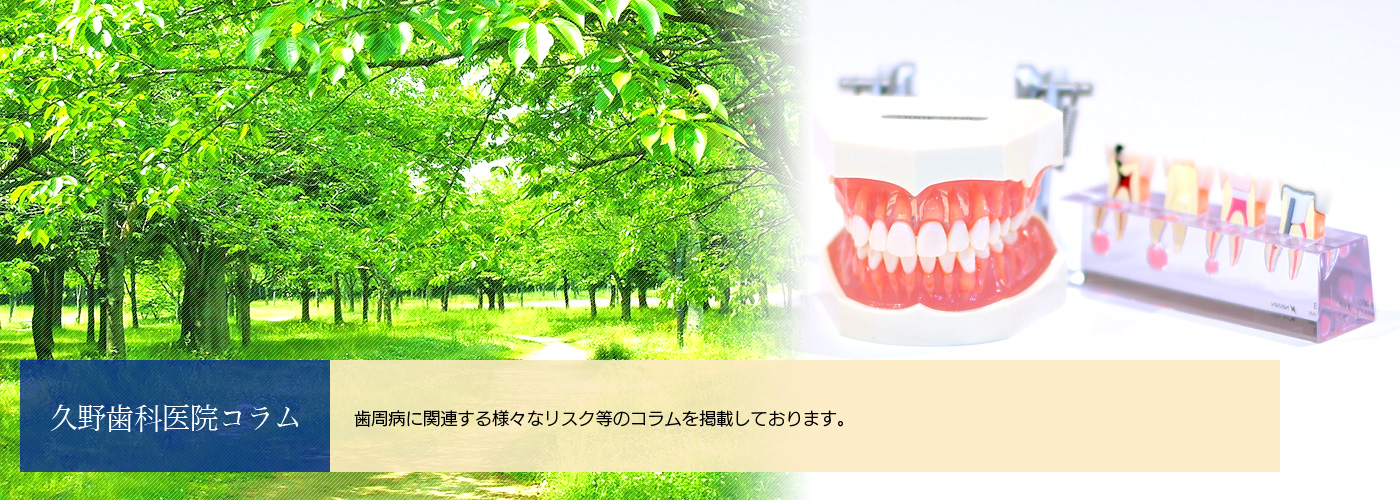

 |
 |
 |
当院おすすめ記事はこちら▼
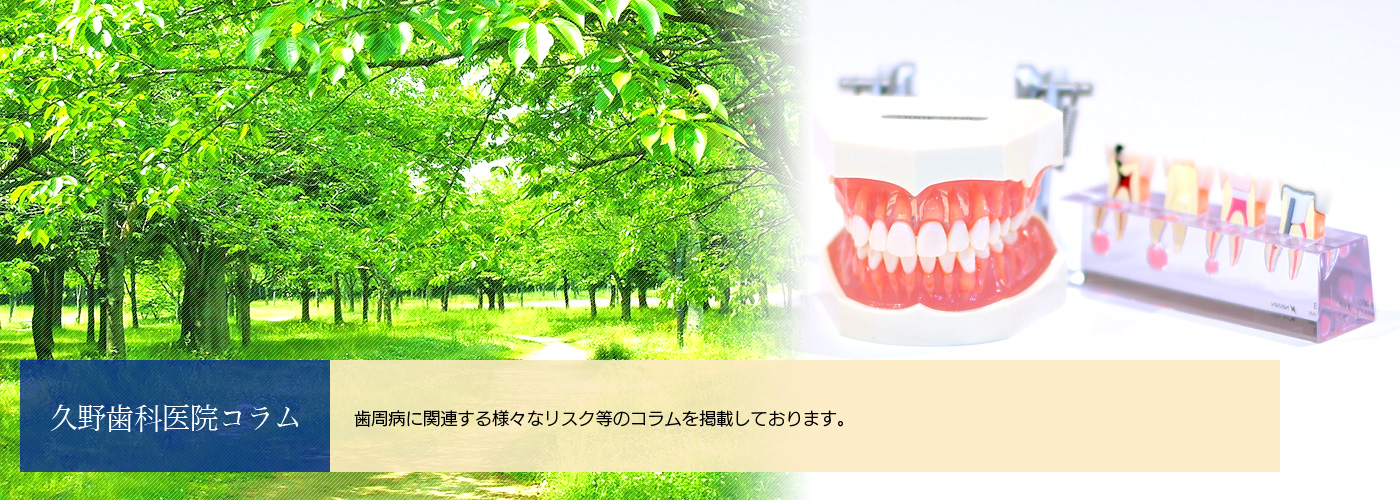

常滑の矯正歯科 久野歯科医院 ≫ 久野歯科医院コラム


お口のなかのけがの起きる事故はどうしておきるのでしょうか?
事故を未然に防ぐには事故の発生を予想して
事故の発生に備えるが大切です。
事故はいつ起こるのでしょうか?
朝、通勤・通学中、昼、部活中、夕方、夜中などに発生します。
事故はどこで起こるのでしょうか?
家のなか特にフローリングの床、舗装した道路、学校の廊下、硬い素材の校庭、駅の階段などで発生します。
事故はどうしておこるのでしょうか?
出会い頭、よそ見などの不注意、けんかなどで発生します。
事故の相手は?
人、遊具、自転車、自動車など。
事故が起こる状況などをイメージして備えることも大切なことです。
口の中は粘膜で覆われていて細かく、細い血管が多く存在します。
唾液が唾液腺から口の中へ分泌されています。
そのため口の中を怪我するととてもたくさん血が出ているように錯覚してあわててしまいます。
口の中や歯と歯の周りの構造を知っておくと
事故が起こったとき、あわてないで対処することができるでしょう。


顔面部に強い衝撃が加わると軟らかい軟組織の中にある硬い歯によって
頬や歯ぐきが傷つき、出血が起こります。
洗浄:
あわてずに砂や石などがあれば口の中をきれいに洗います。
出血部位の確認:
どこから出血しているかをハンカチやガーゼ、ティッシュペーパーなどで抑えながら確認します。
圧迫止血:
出血部位が確認できたらしっかりと出血部位をハンカチやガーゼ、ティッシュペーパーなどでおさえます。
しっかりおさえて歯科へ連絡、来院します。
冷やす:
腫れがひどい場合には氷などで冷やします。
歯が植わっている周辺の骨が折れているときがあります。
周辺の骨(歯槽骨)が折れているとそれに伴って歯の位置がずれることもあります。
歯が欠けてしまったら欠片を集めて歯科医院へ持参してください。
欠片を集めてつなぐことができる時があります。
歯の中から血が滲んできていれば歯髄が露出しているかもしれません。
触らないようにして歯の欠片をもって歯科医院へ来院してください。
歯に強い衝撃がくわわると歯の歯根膜がダメージを受け、
歯がぐらついたり歯を触ると強い痛みが出たりします。
歯根膜が回復するまで安静を保つために健康な両脇の歯まで含めて
ワイヤーを補助にして強力な接着剤で固定します。
強い衝撃で歯が埋まってしまったり大きく動いてしまったりすると
強く歯根膜がダメージを受け、完全脱臼よりも予後不良です。
元の位置に戻して固定を試みます。
強い衝撃で歯が外に飛び出してしまった場合には口の中の洗浄と部位の確認を行い、
飛び出してしまった歯を適切な取り扱いをして急いで歯科医院に持参します。
歯をもとに戻しワイヤーを補助にして強力な接着剤で固定します。

学校などで「歯の保存液」があれば入れて歯科医院へ持参します。
「歯の保存液」の中では歯根膜は4℃で24時間保存されるといわれています。
「歯の保存液」がなければ冷たい牛乳に入れて歯科医院へ持参します。
冷たい牛乳の中では歯根膜は4℃で6時間〜24時間保存されるといわれています。
牛乳は「コーヒー牛乳」のような乳飲料ではありません。
生理食塩水では4℃で30分〜1時間保存可能で極端に保存可能時間が短くなってしまいます。
アルコールに歯を入れることは決してしてはいけません。
歯根膜がすぐに死んでしまいます。
水道水で長時間洗うこともしてはいけません。
歯根膜が死んでしまいます。
砂、土などの汚れはそのままで歯の保存液、牛乳、生理食塩水のいずれかにいれ、
そのまま歯科医院に持参、受診するようにします。
歯を乾燥させてはいけません。湿潤状態を保つことも大切です。
固定後の急激な歯根吸収を招きます。
歯根膜の損傷の程度が予後を大きく左右します。
不運にも「歯の保存液」、牛乳がなければ
飛び出してしまった歯をお口の中に入れて受診してください。
お口のなかの口腔前提部(頬と歯の外側の空間部分)に歯をいれると
歯を飲み込んでしまう心配がありません。
鼻骨の骨折、頬骨の骨折などが発生します。
上顎の骨折は重症の場合が多く、下顎の骨折に比べると起こる
確立は低いのですが歯の周りの骨に多く発生します。
前歯部に多いのですが、これは上顎の前歯の部分が外傷を受けやすいからだと思われます。
歯の破切や歯の脱臼などの硬組織や
唇、歯ぐき、口腔粘膜など軟組織の損傷を伴うことが多くあります。
骨折のよくおきる部位はオトガイ正中部、下顎角部、臼歯部、犬歯部等にみられます。
下顎の骨は口を開けたり閉めたりする筋肉が付いているので
骨折した位置や歯の状態などで様々に骨が変位します。
骨折部位の腫れ、変形、圧痛、咀嚼時や咬合時の痛み、
飲み込む時の痛みなどがあらわれます。
もちろん、上顎の骨折と同様に歯の破切や歯の脱臼などの硬組織や
唇、歯ぐき、口腔粘膜など軟組織の損傷を伴うことが多くあります。
骨折の治療は骨折直後であれば整復をします。局所麻酔下で歯の変位とともになおします。
範囲が大きく骨折箇所が数箇所あったり、変位が大きい場合などは手術が必要になります。
大きな衝撃が加わった部位から離れた部位に起こった骨折を「介達骨折」といいます。
介達骨折は衝撃の加わる方向や部位、強さによって骨折の起こる場所や状態が異なります。
オトガイ部に衝撃が加わった場合には下顎関節部の頚部が骨折します。
両方から挟まれるように下顎角部に衝撃が加われば
圧力で下顎の真ん中(正中部)に骨折が起きる時がございます。