常滑の頼れる歯医者 久野歯科医院です
皆様に役に立つ歯科の情報をわかりやすくお知らせします
愛知県保険医協会の歯科学術研究会に参加・その2
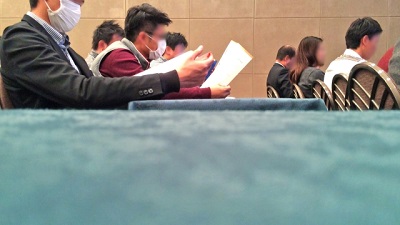
愛知県保険医協会の歯科学術研究会に出席しました
講師:栗田賢一先生(愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座 主任教授
題目:開業医が知っておくと良い口腔外科の知識と技術
栗田先生とのかかわり
講師の栗田先生はかつて常滑市で行われていた歯科健診の「60歳歯の健診と相談」の立ち上げのため、常滑市歯科医師会に助言と協力をしてくださった先生の一人で私が東京歯科大学で研修を終えて、愛知学院大学歯学部の歯科口腔外科で見学していた時にも丁寧に親知らずの抜歯や縫合の仕方を教えていただいた,かけがえのない先生の一人です。
語学力にも優れている先生で、英語で書かれていた外国の論文を楽しそうに読まれていた姿が思い出されます。
尚、「60歳の健診と相談」は現在の常滑市で行われている歯科の年齢別の節目健診の中に取り込まれ、健診項目、健診内容は「60歳歯の健診と相談」が基になっています。
今では一般化している口腔粘膜健診も常滑市は、ほかの地区の先駆けとなっていて、開業医の定期健診にも1項目として取り入れられています。
常滑の歯医者で定期健診、メインテナンスなどを行われている患者様は舌癌に代表される口腔がんで命を落とされる方はいないと思っています。
会場に来ているほとんどの歯医者は栗田先生と何かしらのかかわりのある方が多くいたと思います。
痛みの無い局所麻酔と抜歯
局所麻酔の手順で痛みの少ない局所麻酔の勘所を教えていただきました。
当院でも局所麻酔時には注意をしてなるべく痛みを伴わないように心がけていますが、今回は自分の麻酔注射の手順の参考と確認ができました。
抜歯時に患者様の循環動態のお話では麻酔薬にはいいているエピネフリンの量でも脈拍、血圧に影響を与えることに注意が必要であることをお話ししていただきました。
下歯槽神経の損傷は伝達麻酔時、下顎の埋伏した親知らずの抜歯、インプラントの植立手術時に注意が必要で舌神経の損傷はやはり親知らずの抜歯時の麻酔で注意が必要なことを説明していただきました。
特に親知らずの抜歯の時に起こる可能性のある下歯槽神経の損傷によるしびれ感などを回避するための一つの方法として親知らずの歯冠部のみ取り除き、歯根部を残す「歯冠部切除術」を紹介していただきました。
顎関節症
顎関節症の診断から治療までの全般についてお話しいただきました。
顎関節の構造から正常な開閉運動について実際に関節の動きを動画にしたもので詳しく解説した後に顎関節の診査と診断法について説明していただきました。
なかでも、顎関節の機能の総合評価は顎関節症の患者様の障害度がわかり、限られた時間の中ですぐ役立つものでありました。
続いて顎関節症の病態と病型の説明に入り、病型それぞれの治療法について解説がありました。
病型がわかることで診療室での具体的な処置方針が立てやすくなります。
開業医から高次医療機関(大学病院、病院の歯科口腔外科)への紹介基準などについてもお話しいただきました。
顎関節脱臼
習慣となってしまった顎関節の脱臼は高齢者によくみられ、認知症が伴いますと、口が閉じられないために誤嚥性肺炎を起こす可能性が高くなります。
当院にも高齢者の方で顎関節脱臼を起こす患者様がいらっしゃるため興味深く、講演を聞きました。
脱臼防止の手術の図から脱臼の整復のイメージにつながりました。
骨粗鬆症と薬剤顎骨壊死の関係
最後に薬剤顎骨壊死についての説明がありました。
骨粗鬆症の治療薬のビスホスホネート製剤に発生確率は低いのですが治りにくい骨髄炎の副作用があることは歯医者として注意しなければならない重要な事柄です。
最近ではビスホスホネート製剤だけでなく、皮下注射による新しい骨粗鬆症の薬が登場してきています。
骨粗鬆症の治療薬は高齢者の骨折を防ぎ、寝たきりになるのを予防できる大切な薬ですが選択的に顎の骨に集積して10年以上残留するといわれています。
口腔内は不潔になりやすいので、骨髄炎が発生しやすい環境にあります。今後、高齢者がさらに増加して骨粗しょう症の治療薬の長期の連用が顎骨壊死のリスクを高める可能性も低くないと思われます。
私たち歯医者は患者様への易しい説明に努め、ご理解を深めていただくことも顎骨壊死の予防には必要です。
歯医者は薬剤顎骨壊死については常に新しい情報を知っておくことも大切です。

今回の講演は最近のトレンドではなく、歯医者として必要不可欠な事柄について、時に顎関節症については改めて多くのことを学びました。













